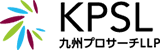肺がんとは?
肺がんは、気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化したものです。 進行すると、がん細胞は周りの組織を壊しながら増殖し、血液やリンパ液の流れにのって転移することもあります。転移しやすい場所はリンパ節、反対側の肺、骨、脳、肝臓、副腎です。
肺がんは、組織型によって、非小細胞肺がんと小細胞肺がんの2つに大きく分けられます。発生頻度が高いのは非小細胞肺がんで、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんに分類されます。中でも最も多いのが腺がんで、一般には「肺腺がん」ともいいます。小細胞肺がんは、非小細胞肺がんと比べて増殖速度が速く、転移や再発をしやすい腫瘍です。
非小細胞肺がんと小細胞肺がんでは、治療方針が大きく異なるため、検査によって組織型を確認してから治療を開始します。
主な肺がんの組織型とその特徴
肺がんの組織型
<腺がん>
唾液の出る唾液腺や胃液の出る胃腺などの腺組織とよく似た形をしているがんのことです。腺がんは、多くの場合、肺の奥のほう(肺野部)の細かく枝分かれした先にできます。女性やタバコを吸わない人にできる肺がんの多くがこの腺がんで、肺がん全体の半数程度を占めます。
<扁平上皮がん>
皮膚や粘膜など体の大部分をおおっている組織である扁平上皮によく似た形をしているがんのことです。扁平上皮がんはタバコとの関係がきわめて濃厚で、大部分は肺の入り口に近い肺門部にでき、肺がん全体の25〜30%を占めます。
<大細胞がん>
扁平上皮や腺など、体の正常な組織に似たところがないがんのうち、細胞の大きなものを大細胞がんといいます。主に肺の奥のほう(肺野部)の細かく枝分かれした先にできます。大細胞がんは、肺がんのうち数%を占めるくらいです。
<小細胞がん>
扁平上皮や腺など、体の正常な組織に似たところがないがんのうち、細胞の小さなものを小細胞がんといいます。小細胞がんは、他の組織型に比べて、発育成長が早く、転移もしやすいのが特徴です。多くは肺の入り口に近い肺門部にでき、肺がん全体の10〜15%を占めます。
肺がんの治療方法
1. 外科療法:根治手術(肺葉切除+リンパ節郭清)
2. 薬物療法
a. 化学療法薬:・シスプラチン ・カルボプラチン ・ペメトレキセド ・イリノテカン
・ドセタキセル ・ゲムシタビン ・パクリタキセル ・ビノレルビン
・エトポシド ・テガフール
b. 分子標的薬: [EGFR-TK] ・ゲフィチニブ ・エルロチニブ ・アファチニブ
[ALK-TK] ・クリゾチニブ ・アレクチニブ ・セリチニブ
[抗VEGF抗体薬] ・ベバシズマブ
[免疫チェックポイント阻害薬] ・ニボルマブ
3. 放射線療法:根治照射、予防的全脳照射、緩和照射
白金製剤
白金製剤(シスプラチン、カルボプラチン)が肺がんの中心的な薬物です。
白金製剤のどちらか1剤をベースとし、化学療法薬をもう一剤加える2剤併用レジメンが基本となります。
白金製剤は、構造中の白金(プラチナ、Pt)がDNAの塩基に架橋を形成することで、DNAの複製や転写を阻害します。この結果、がん細胞のアポトーシスが誘導され、がんは縮小します。
微小管阻害薬
主な微小管阻害薬には、タキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル)とビンカアルカロイド系(ビノレルビン)があります。タキサン系はチューブリンの脱重合を阻害、ビンカアルカロイド系は重合を阻害することで微小管機能を傷害し、細胞分裂を停止させ、結果的にアポトーシスが誘導されます。
トポイソメラーゼ阻害薬
DNA複製部位で2本鎖らせん構造がほどかれていくと、他の部位にねじれ、ゆがみが生じます。このねじれたDNAを切断して、ねじれを修正した後に再結合するのがDNAトポイソメラーゼです。2本のDNA鎖のうち、1本を切断して再結合するのがトポイソメラーゼ I、2本とも切断して再結合するのがトポイソメラーゼ IIです。
トポイソメラーゼ阻害薬は、これらの酵素の働きを抑制することによりDNAの切断と再結合を阻害するため、がん細胞は正常な分裂ができなくなり、細胞死へと導かれます。
トポイソメラーゼ I阻害薬としてイリノテカン(CPT-11)が、トポイソメラーゼ II阻害薬としてエトポシドがあります。
なお、イリノテカンは体内で活性代謝物であるSN-38に変換されて作用しますが、SN-38は肝臓で主にUGT1A1によりグルクロン酸抱合を受け不活性化されます。UGT1A1遺伝子には遺伝子多型があり、野生型に比べて代謝活性が低くなる変異体が存在します。60種以上の多型が知られていますが、特に*6と*28が重要で、これらの遺伝子変異を持つ場合、副作用の重症化、頻度の増加がおこるため、UGT1A1遺伝子多型はイリノテカンの副作用を予測するバイオマーカーとして用いられます。
分子標的薬
化学療法薬は、核酸の合成、細胞分裂といった細胞増殖そのものを阻害しますが、分子標的薬は、その上流にある刺激・シグナル伝達を阻害し、細胞増殖をおこさせないようにする薬です。
分子標的薬は、薬物の構造・分子量の違いから、抗体薬と小分子薬に分けられます。
抗体薬は特定の分子(抗原)に対するモノクローナル抗体であり、分子量が大きいため、細胞外、細胞表面で作用します。受容体活性化阻害、抗体依存性細胞傷害(ADCC)、補体依存性細胞傷害(CDC)により、がん細胞の増殖を抑制します。
小分子薬は分子量の小さい化学物質であり、細胞膜を透過して細胞内で作用し、多くは酵素阻害薬として作用します。
EGFRチロシンキナーゼ阻害薬
小分子薬であり、EGFRの細胞内領域のチロシンキナーゼ活性を抑制し、シグナル伝達を阻害します。
EGFR遺伝子変異陽性例に有効です。
ALKチロシンキナーゼ阻害薬
小分子薬であり、EML-ALK融合蛋白質などの異常活性化ALKのチロシンキナーゼ活性を阻害します。
肺線がんにおけるドライバー遺伝子発現頻度
免疫チェックポイント阻害薬(抗PD-1抗体薬)
T細胞の表面には、「異物を攻撃するな」という命令を受け取るためのアンテナがあり、がん細胞にもT細胞のアンテナに結合して、「異物を攻撃するな」という命令を送るアンテナがあります。これらのアンテナが結合すると、T細胞の異物攻撃にブレーキがかかり、がん細胞は排除されなくなります。このように、T細胞にブレーキがかかる仕組みを「免疫チェックポイント」といいます。免疫チェックポイント阻害薬は、T細胞やがん細胞のアンテナに作用して、免疫にブレーキがかかるのを防ぎます。
現在、臨床応用が進んでいる主な免疫チェックポイント阻害薬には、抗CTLA-4抗体、抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体などがあります。
活性化T細胞上に発現しているPD-1が、がん細胞や抗原提示細胞に発現したPD-L1と結合すると、T細胞活性化は抑制され、がん細胞の免疫逃避を引き起こします。抗PD-1抗体は、T細胞上のPD-1に結合してPD-1とPD-L1の結合を阻害することにより、抑制シグナルの伝達をブロックしてT細胞の活性化を維持し、抗腫瘍効果を回復します。
抗PD-1抗体薬として有名なのは、ニボルマブ(商品名:オブジーボ)です。2018年に本庶佑 京都大特別教授が本薬剤の作用機序に関してノーベル医学・生理学賞を受賞しています。